Report Project
論文活動(総合学習)

論文活動について
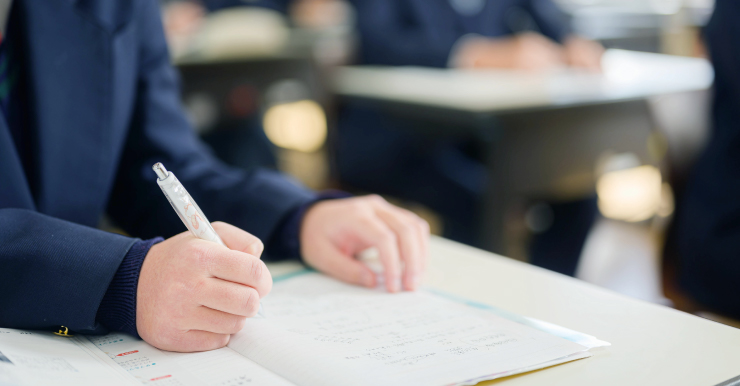

論文活動で育むリテラシー能力
「読む・書く・話す」力を
身につける!
1999年度から継続してきた論文活動は1期生からの伝統的な活動です。
生徒は自らの関心に基づいたテーマを選び、1年間にわたって8000字以上の論文を執筆することに取り組んでいます。このプロセスで、生徒は「読む・書く・話す」という大学生や社会人になってからも必要とされる能力の基礎を身に付けることを目的としています。論文が完成した後には、論文全員発表会が行われ、生徒たちは1年間の成果を発表します。さらに、優秀な成果を収めた6人の生徒は、全校生徒の前でプレゼンテーションを行います。また、自分の論文内容を英語でプレゼンテーションする活動も取り入れており、生徒たちは主張を的確に伝えるための表現力や話し方を磨くことができます。
論文活動の流れ
- 2年生3学期 テーマ決め開始
- 3年生1学期 担当の先生決定
研究計画書作成 - 夏休み フィールドワークなど実施
- 2学期 論文の完成
- 3学期 論文全員発表会
優秀論文発表会
論文活動
テーマ一覧
令和5年度(25期生)
論文活動テーマ一覧
- 「批判的な笑い」を日本で発展させるには
- 〇×ゲームに必勝法はあるのか
- AIの進化とこの先の人間
- AIやロボットによる生活の影響
- BLACKPINKはなぜ世界で成功しているのか
- VOCALOIDをうたコンに出演させるには
- 悪役とは何なのか
- あなたはできる?かかとをつけてしゃがむ方法とは
- アニマルセラピーをもっと日本で普及させるには
- アニメ及び漫画文化について
- アマチュア無線でSDGs11ゴールを達成する
- 伊方町を活性化させるには
- 異次元の人口減少対策
~もし私が松山市長になったら~ - 衣装デザインとキャラクターの構成
- 依存症とその危険性
- イヌの感情表現
- 嘘と人
- 歌い手オタクから読み解く「推しを推したくなる理由」
- 売れる!アイドルの作り方
- 英語力を上げるには~私の実験結果~
- 愛媛県に遊園地を開設するには
- 愛媛県の貝の漁獲量・多様性を回復するには
- 愛媛県の人口減少を食い止めるには
- 愛媛県の人口問題と魅力について
- 愛媛に遊園地を作るには
- お金を増やすことについて
- 音が脳に与える影響
- おならの臭さ・音の原因と腹の関係性と、その解消法
- 音楽と感情の関係性
- 音楽による勉強中の脳に与える影響
- 音楽療法の現状と課題?病院見学を通して?
- 音楽を聴く心理
- 外国人留学生を幸せにするには
- 過去からの継承~昔話から~
- 学校生活で本当にすべきこととは
- 仮面ライダーについて
- カラーセラピーとハーバリウムの繋がり
- カラスのゴミ荒らしをなくす
- 仮に猫を飼うのに免許が必要だとしたら、試験はどんな内容なのだろう
- 瓦の可能性
- 環境と生物
- 観葉植物にリラックス効果はあるのか
- 緊張による体への影響
- 筋トレとボディメイク
- ゲームの魅力
- 月での快適な暮らし
- 現代のテレビについて
- 校則とルールの必要性
- 心地よい音楽とは-jpopから学ぶ-
- 異なる方言の発生についてーなぜ日本という同じ国で異なる言語形態が発生したのかー
- 子ども食堂の可能性
- 昆虫食の可能性
- 最強のポケモンについて
- 済美平成校生にとって良いお弁当とは
- 詐欺やインターネット上の違法行為を止めるには
- サッカー日本代表が強豪国と対等に戦うためには
- 殺処分を減らすために
- 茶道を習うことによるメリット
- 自分が見たい夢を見るには
- 社会性昆虫の社会性
- 社会における噂とは
- 習慣形成をするためには
- 重力の本当 未解明の重力の謎
- 小学生の放課後の居場所
- 植物の成長促進を促すためには
- 信号機の影響と交通事故の関係性
- 睡眠について
- 睡眠の質を向上させるには
- 好き嫌いについて
- スポーツ中継の面白み
- スマートフォンの使用を開始する推奨年齢
- スマホが本当に悪いものなのか
- 正義とは何か~現代の正義は正しいのか~
- 世界に通用する愛媛の魅力
- 誰にでも伝わりやすいピクトグラム
- 誰もが自分らしく生きるために?性の多様性?
- 中学生としてQOLを高めるには
- 中高生の歯の健康を保つには
- 中高生をターゲットとした色のデザイン・マーケティング
- 次はこれだ!コンテンツ大国Nipponのヒット予測
- ディズニー・ヴィランズ~悪役もヒーローになれるのか~
- ディズニーキャストから学ぶ人を幸せにする方法
- デザインにおける黄金比の可能性
- デジャブの謎
- 電気自動車は本当にエコなのか
- どうすれば人気のあるテーマパークがつくれるのか
- なぜ嫌な音を聞くと鳥肌が立つのか
- なぜ愛媛県大洲市は「世界の持続可能な観光地」世界一に輝いたのか
- なぜ日本の人口は減り続けるのか?原因とその対策~
- なぜポケモンは人気なのか
- 日本人はお金をどう思っているのだろうか?
- 日本と海外の読書教育
- 日本と韓国のアイドルから考える、次世代のアイドルの在り方について
- 日本文化の移り変わりからみる文化の受け継ぎ方
- 日本昔話は人々に何を伝えていくのか
- ハンカチについて
- ハンドボール日本代表が世界選手権で優勝するには
- 微生物について
- 人のために活躍する犬について
- 人はあなたのことを気にしていない
- 人はなぜテーマパークに行きたがるのか?テーマパークにかけられている魔法~
- 人は夢から何を得られるのか
- 人をひきつける医療ドラマ
- 百人一首と聴力の関係
- ファスト文化の功罪
- 夫婦別姓を実現するには
- 不快な音について
- 筆箱と性格の関係
- プロサッカーにみる日本人選手の海外移籍と日本企業の海外進出との繋がりについて~そこから考察すること~
- 分析心理学における仮面について
- 文房具と共存するとは
- ペットロボットをより多くの人に必要だと思ってもらうにはどうすればいいか
- ヘルプマークの今とこれから
- 本能寺の変の黒幕は存在したのか 信長が裏切られないためにはどうすれば良かったのか
- マイペースの定義
- 松山の交通について
- 漫画、アニメの人気度の違いについて
- 身近な感染症への向き合い方
- 未来を生き残る仕事
- 昔のバラエティの企画は、今の時代放送できるのか~TVと時代の変化~
- 野球の試合で勝つには
- 野菜を先に食べることによる身体の変化
- 夢と脳、体の関係について
- より安全で速く走る自動車をつくるためには
- ライブのチケットを公正に行き渡らせる、よりよい方法は?
- 和食文化を無くさないために
旺文社学芸
サイエンス 入選一覧
本校では3年生で作成した論文を、後期課程で旺文社が主催している学芸サイエンスコンクールに応募しています。
応募を始めた6期生から、多くの生徒が入賞しています。
※( )内はサブタイトル
金賞
| 期別 | 氏名 | 論文タイトル |
|---|---|---|
| 00 | ○○ ○○ | 論文タイトルテキストテキスト (サブタイトルテキストテキスト) |
| 00 | ○○ ○○ | 論文タイトルテキストテキスト (サブタイトルテキストテキスト) |
銀賞
人文社会科学研究部門 部門賞
| 年度 | 賞 | 期別 | 氏名 | 論文タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 2017年度 (第61回) |
銀賞 | 18 | 松岡 歩未 | まちづくり (内子座100周年からみえること) |
銅賞
自然科学研究部門 部門賞
| 年度 | 賞 | 期別 | 氏名 | 論文タイトル |
|---|---|---|---|---|
入選
| 期別 | 氏名 | 論文タイトル |
|---|---|---|
| 6 | 土居 美沙季 | 発酵は人類を救う (古くて新しい技術 FT革命) |
| 7 | 井上 知謙 | 千年釘 (釘に込める情熱とは) |
| 8 | 大西 ひかる | ストリートチルドレン |
| 8 | 高橋 幸嗣 | 集中力 |
| 9 | 岡本 唯 | 在韓被爆者問題を考える (忘れら去られた犠牲者たち) |
| 10 | 井手 梓 | よさこい! |
| 11 | 和氣 由布子 | どんでん返しの魅力 (オー・ヘンリー作「赤い酋長の身代金」から探る) |
| 11 | 大藏 あゆみ | ダイラタンシー (その現象がおこるには) |
| 12 | 阿部 沙樹子 | 「千と千尋の神隠し」を観る適当な年齢 |
| 12 | 上岡 みなみ | 視力 |
| 13 | 秋山 馨 | 日本人の桜観と死生観 |
| 13 | 武智 有紀 | 地震予知 |
| 13 | 白石 沙織 | まちづくり (『温故知新』まちを見つめる) |
| 14 | 飯尾 隼人 | 在宅医療 (~私達の生活に生きる医療~) |
| 14 | 髙村 友美 | 錯視デザインにおける心理的効果と実用性 (よりよい街にするために) |
| 15 | 奥村 南々子 | 親子関係について |
| 15 | 高橋 慶丞 | 重信川汽水域におけるカニの生態系調査 (アカテガニを救うために) |
| 16 | 大澤 史哉 | 日本にデジタル教科書を導入するためには |
| 17 | 大惠 奏歩 | 少子高齢化 (地方文化を守るためには) |
| 17 | 戸田 裕子 | 水 (軟水と硬水) |
| 19 | 鍵山 実玖 | 人を魅了するプレゼンテーションとは |
| 21 | 矢野 陽菜 | サーキュラーエコノミー |
| 22 | 中野 優 | トップアスリートが最高のパフォーマンスを発揮できる理由 |
| 23 | 澤近 大地 | 日本の教育の問題点 (日本の子供たちの精神的幸福度を高めるために) |
| 24 | 安藤 橙希 | 色の見え方と多様性について |
| 24 | 濵田 蕾 | 正義とは何か (より善い社会を築くために) |
6年間の総合学習(探究)
| 学年 | 年齢 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
| 1年 | 13 歳 |
インタレストスタディーズⅠ
| 新入生迎え入れ企画を成功させよう | |
| 2年 | 14 歳 |
インタレストスタディーズⅡ
| 研修旅行の自主研修ルートづくり | |
| 3年 | 15 歳 | インタレストスタディーズⅢ(論文活動) | ||
|
|
| ||
| 4年 | 16 歳 |
世界に目を向けよう
| 進路を探究しよう
|
世界に目を向けよう
|
チャレンジ論文(外部コンクールへの投稿) | ||||
| 5年 | 17 歳 |
学校のリーダーとして
ENAGEED(他者の視界を
描く力) |
学問分野の探究
|
学問分野の探究
|
チャレンジ論文(外部コンクールへの投稿) | ||||
| 6年 | 18 歳 |
社会に出るために知っておくべきこと
発表の方法を学ぶ
ENAGEED(自分が選んだ道を正解にする力)
| ||
総合的な学習(探究)の時間
済美平成学
主に1年生では済美平成中等教育学校の歴史・建学の精神・校訓の意義などを学び、本校での生活をより充実したものとする。
『課題研究メソッドStart Book』
2年生では、3年時の論文活動を迎えるために、学び方、調べ方を学び、興味・関心の幅を広げ、実際に探究活動をしてみる。
『ENAGEED』
「社会(世界)のなかの私たち」
4年生では、SDGsなどを題材に、現在の世の中の諸問題について考え、自らの人生について考える。
「進路探究」
4年生での文理選択で重点的に行うが、5年・6年と自らが進む進路について探究していく。
「学校行事を成功させよう」
5年生ではオープンスクールのホスト、スポーツカーニバルのリーダーなど、学校行事を中心となって運営する。
「新書ゼミ」
5年生では新書を題材として、教員やクラスメイトから、テキストの読み方を学ぶ。







この活動を通じて、図書館で本を読んだり映画をみたりして、ウォルト・ディズニーの魅力の本質を探る過程で、自分の頭で整理し、まとめ、文章化する力が身につきました。この能力は、大学の工学部で京都の神社の環境や役割を研究する際にも大いに役立ちました。近隣の小学校でアンケート調査を実施し、統計分析を行うアイデアも、済美平成での論文活動があったからこそ生まれたものです。
就職活動においても、論文活動でインプットとアウトプットで苦労したことが、履歴書で自分の魅力を効果的に表現し、自己PRを行うことにつながりました。社会人になってからも、自分の意見を明確に表現する場面が多々あります。そのような時にも、論文活動で培った力が必要不可欠となります。
論文活動は生涯にわたって役立つスキルを磨く貴重な機会だったと思います。一度経験したことで、他の人よりも少し手前でスタートラインに立てたような感覚があります。これは、どんな分野でも通用する大切な財産だと感じています。